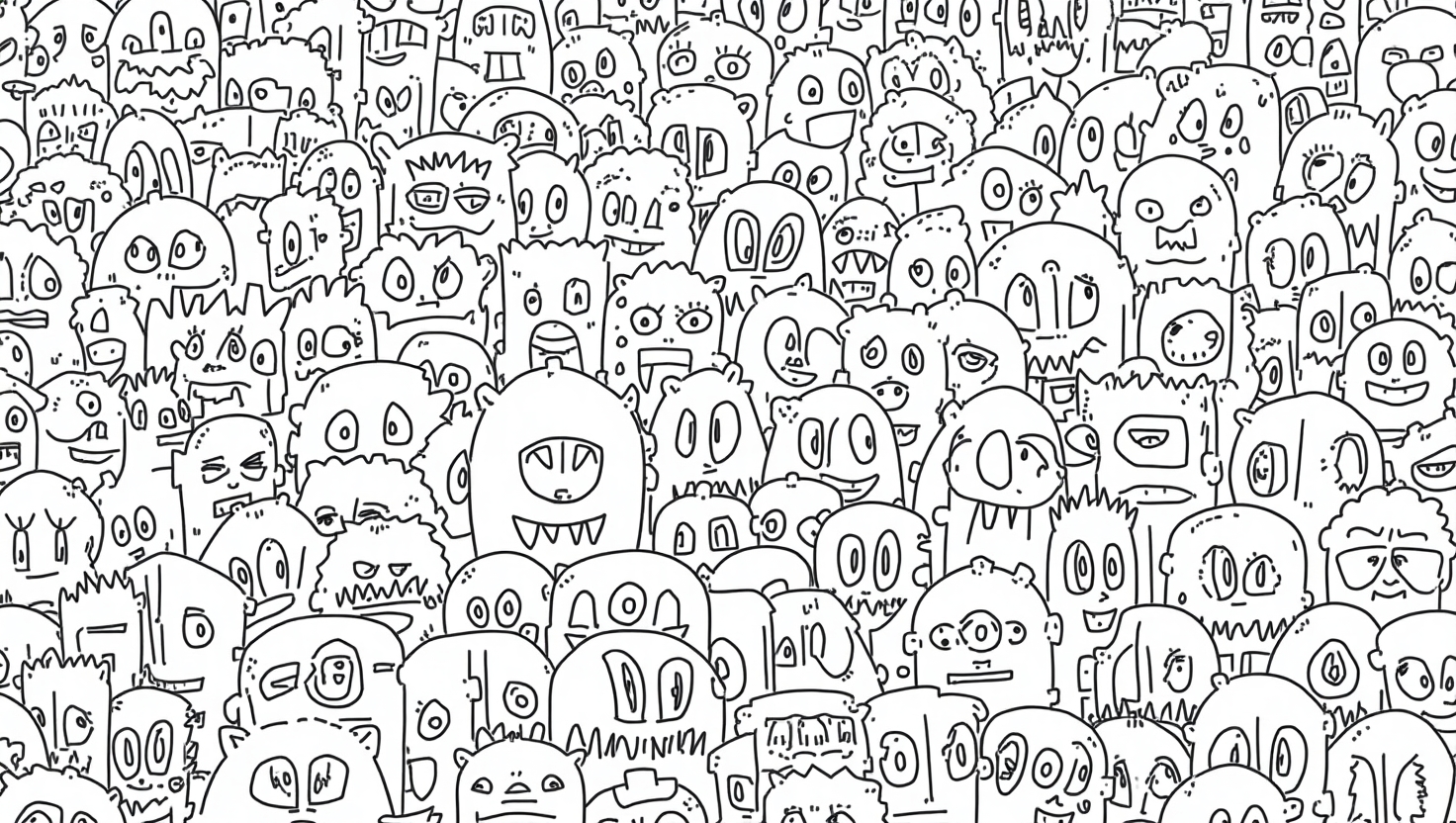ゾンビファイル
今から十数年前に作られたExcelやAccessでのマクロプログラムが今もなお残り続けている。表計算ソフトと呼ばれるデータベースに似たツールを背景にユーザーインターフェースやロジックを付け足したものである。もはやゾンビファイルと言っても過言ではない。これらのシステムは当初の目的を果たしていても、時代の変化とともに保守性や拡張性に大きな課題を抱えるようになっている。
作成者不明問題
社内に残る通称「マクロ」は、今はいない人が作成していたり、一部の人が独自に作ったものであることが多くある。作った人がいる場合はまだしも、退職している場合はその中のプログラムも見ることができないので、いつ止まるか分からないシステムを業務の中心で使い続けていくことになる。このような状況では、エラーが発生した際の対処法が不明で、業務継続に深刻なリスクをもたらす可能性がある。
市民開発解決法
ブラックボックス化したマクロを情報システム部に解決をお願いするのではなく、市民開発にて解決するには多少のコツが必要になる。ポイントは完全にブラックボックス化している状態や、何から手を付けていいか分からない状態のマクロ群は、残念ながらまずは専門家に情報の整理を依頼することが必要になるだろう。自社だけでの解決を試みる前に、適切な専門知識を持つパートナーとの連携を検討することが成功への近道となる。
専門家活用法
専門家に依頼したほうがいい理由として、マクロファイルの解析だけを切り離した作業としてしまうと、その後の市民開発へ繋ぎにくくなるからである。マクロファイルのインプット/アウトプットを解析した上で、それをどのように今後の市民開発のベース作りに活かすのか。ITコンサルやシステム開発会社の腕の見せどころである。単純な解析作業ではなく、将来的な発展性を見据えた戦略的なアプローチが求められる領域といえるだろう。
まとめ
ExcelやAccessはMicrosoft社の製品であるので、そのままMicrosoft社が提供するPower PlatformやPower Appsへの移行がスマートである。間違ってもマクロをスクラッチ開発でのWebシステムに移管すべきではない。親和性の問題や閲覧性などに課題がのこることが多いようである。