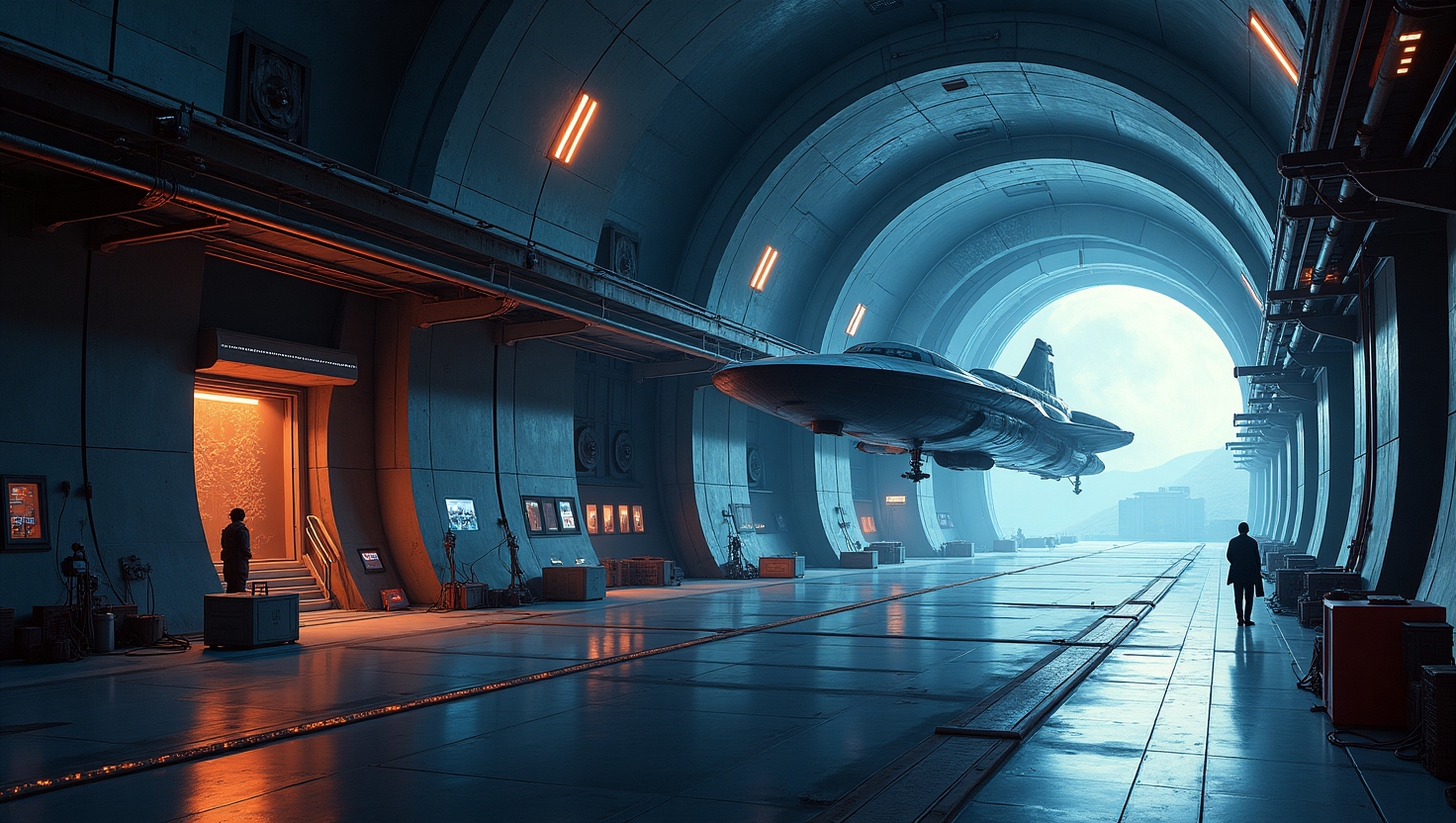市民開発の正体
市民開発(Citizen Development)とは、IT部門やSIerに依存せず、業務部門などの非エンジニアが自らアプリケーションを作成する取り組みを指す。従来は「プログラミングができないと無理」と思われがちだったが、現在ではノーコード・ローコードツールの登場により、非技術者でも業務に必要なツールを構築できるようになった。代表的なものとして、SaaSベースの業務アプリやMicrosoft Power Platformなどがあり、これにより業務現場の課題解決が加速している。
IT不足とマクロの功罪
市民開発が注目を集める背景には、深刻なITエンジニア不足がある。人手が足りないなら自ら開発するしかない——この流れが市民開発を後押ししている。その原型とも言えるのがExcelマクロである。かつて現場では、個人PC上で動作するマクロが業務改善ツールとして使われていたが、多くが属人化し、結果として保守不能な“遺産”となってしまっている。
マクロの限界
Excelマクロの最大の弱点は「ファイル単体依存」である。複数人での同時使用や、プログラムの共有に極めて不向きである。マクロ付きファイルをコピーすれば、そのコピーごとに独立した修正が可能となり、誰がどのバージョンを使っているのか把握が困難になる。しかも、更新履歴の管理も難しく、組織全体の業務統一を図るには限界がある。こうした特性が、非効率と混乱を招く要因となっている。
マクロの呪い
属人化の果てに起きるのが「ブラックボックス化」である。Excelマクロにパスワードがかけられ、開発者も不在、しかし業務には不可欠——そんな状態が現場には数多く存在する。これらは情報システム部の管理外にある「野良プログラム(シャドーIT)」と呼ばれ、セキュリティリスクを高める要因でもある。結果として、誰も触れず、誰も捨てられず、今も現場の根幹に鎮座している。まさに、手遅れになる前に対処すべき課題だ。
まとめ
市民開発は、Excelマクロに代わる次世代の業務改善手段となり得る。ローコード・ノーコードの活用により、野良プログラムの乱立を防ぐには、組織としての運用ルールとガバナンスの確立が不可欠だ。アタラキシアDXでは、Power Appsを活用し、手遅れになる前にブラックボックス化したマクロのリプレイス支援を行っている。